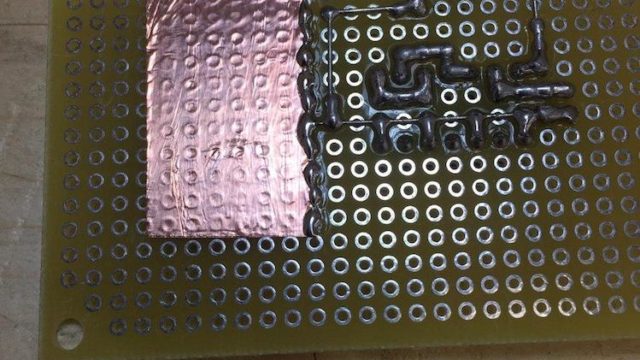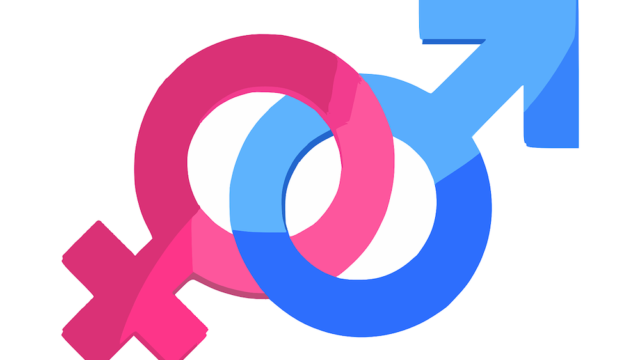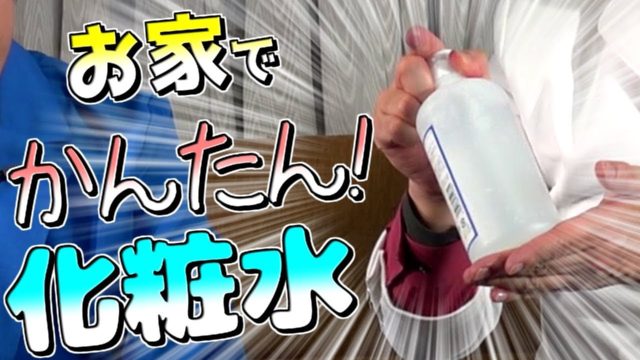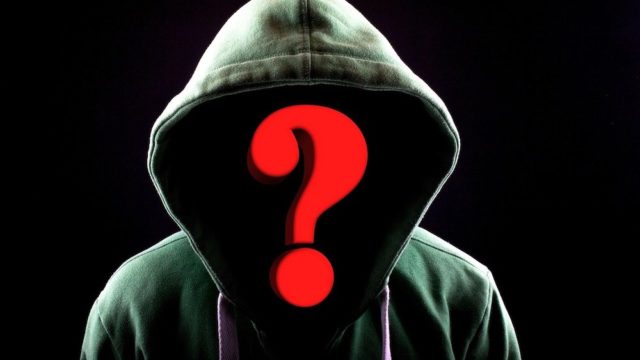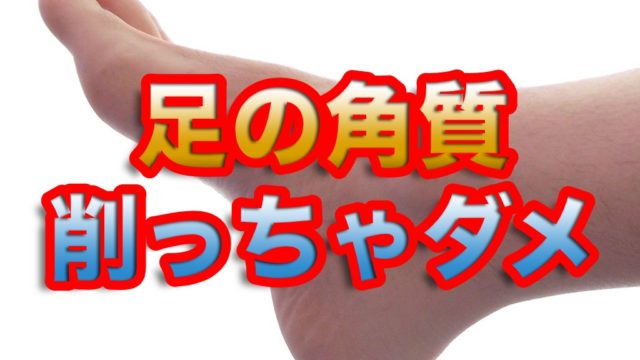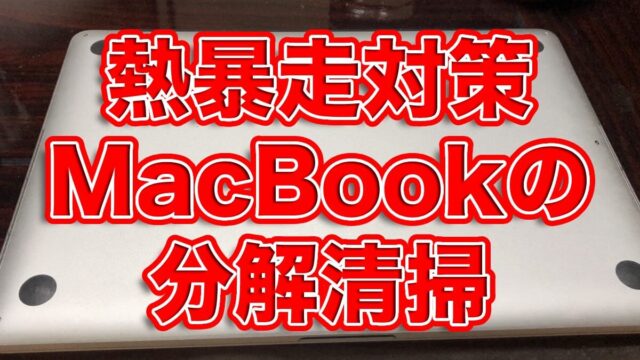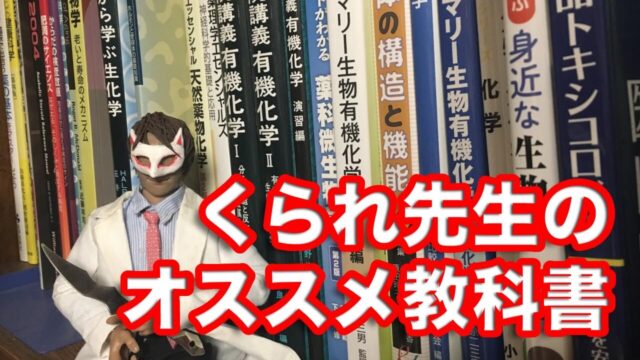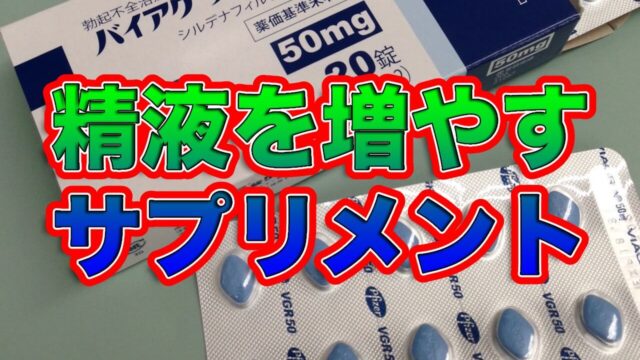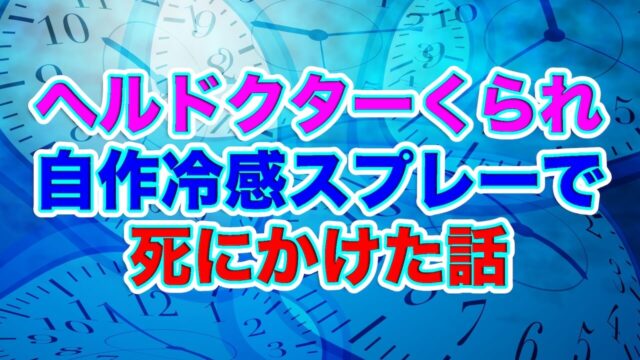初出:2025/04/28

やあやあ、ツナっちくん、この植物を見てくれ!

おお、なんか綺麗な赤い実で、美味しそうですね。

うん、ほんのり甘いよ。ちょっと味見してみる?

・・・くられ先生、何か企んでますよね。食べて大丈夫なんですかコレ?

・・・・・・(ニッコリ)

出たよ! これ絶対食べちゃ駄目な奴じゃないですか!!

そんな訳で今回は日本三大毒草の一つ「ドクウツギ」の話です。

あれ、居たんだJoker。

ええ最初から・・・本当に食べようとしたら止めないといけないじゃないですか。
日本三大毒草「ドクウツギ」の話
Twitter(自称X)で、ドクウツギが話題になっているのを見かけました。
トリカブト、ドクゼリ、そしてドクウツギと、日本三大毒草に数えられるものですが、しかし、2、3粒の実を口の中で味わうだけで死んでしまうような猛毒の植物なんでしょうか?
ドクウツギについては、拙著「アリエナイ毒性学事典」でガッツリ解説しておりますが、今回はその原稿の一部を抜粋してお届けします。
気になる人は、お買い求めいただけると、とても嬉しいです。ボクが。
さて、「アリエナイ理科」シリーズでは、この植物に対してけっこう掘り下げてきているため、既刊の読者であればご存じかと思いますが、アレです。
そのあまりの危険性から、かつては駆除対象にもされ、現在も大規模群落が見つかるとニュースになるような植物です。毒草の本には必ず掲載されているものの、気がつけば駆除が過ぎて、絶滅寸前、もはや日本では幻の植物となってさえいます。
園芸ルートに出回ることもなく・・・希に出回ってもすごい値段が付く有様で、栽培も困難・・・というこの怪しくも儚い植物について、伝説から本当の姿までご紹介しようと思います。
生きた化石・ドクウツギ
まずドクウツギという植物を見てみましょう。

ドクウツギの花


実を付けたドクウツギ。
日本ではドクウツギ科、ドクウツギ属、ドクウツギと一種のみ存在します。類似の植物は無く、全く孤立した種で、植物学的には謎の多い存在です。
猛毒の実をつける・・・といっても、その果肉は、果実の原型である果実化する花弁を持つ、化石でしか見られないような特徴を持ち、言うなれば生きた化石とも言える存在です。恐竜の絶滅とほぼ同時期、白亜紀後期から出現した、果実をつける植物としては最古に近い植物といえます。
実際、種は果実に完全に埋没しておらず、やんわりと独立した太った花びらのような果肉に包まれた原始的な構造をしています。
さらに分布も謎で、チリのごく一部、フランス、イタリアの地中海沿いの一部、ヒマラヤ山脈、ニューギニア、そして日本。いずれも地理的にはまったく縁もゆかりもない感じの点在して、日本とほぼ同じモノが生えています。
実はこれ、新生代 約6430万年前の大陸の赤道直下の名残ではないかと言われているのです。当時、上記のエリアはいずれも熱帯地方であり、それが大陸移動と共に各地に散り、現在も細々と生きながらえているという説があります。
生きた化石と呼ばれる生物は限定された環境で細々と生き残っていることが多いのですが、ドクウツギもまた、極めて限られた環境でしか生きられない弱い植物です。
育てるのがとても大変な毒草
かつて山歩きで、ようやくドクウツギを発見し、なんとか掘り起こし家に持ち帰った事があります。
しかし、少し折れただけの枝は、すぐに萎れ、その後復活すること無く散り、見るも無惨に枯れました。
再度、採取を・・・と思ったら、元の株を採取する際に少し枝葉が折れただけで、こちらも無残に縮み、びっくりするくらいに弱っていたので採取を断念した覚えがあります。
奇跡的に採取した株が復活してきたので、栽培を続けてみますが、水枯れに弱く、水が多いと根腐れを起こし、枝葉は折れやすく、折れた枝は大半が枯れ落ちる。肝心の毒も昆虫には無毒らしく、ヨトウムシを初め、様々な虫の餌食になり、カメムシまで大量にたかる始末。
カメムシに刺された枝はやはり枯れ、花芽は二年目以降の枝にしか出来ないのですが、冬には夏場育った枝の大半は根元まで枯れて、花芽をつけることができる枝自体がそもそも少ないという・・・しかも結実した枝は弱り、大半がそのまま枯れ落ちることもままあります。

ドクウツギ二年目の株
もはや生きる気力を感じ取る方が難しいレベルのワガママ植物で、現在もなんとか維持していますが
地域にはびこり、人の命を狙う極悪な毒草・・・というイメージからはほど遠いのが正直な感想と言えます。
しかし、その危険な果実を味見してみると、ほんのりと青臭い中に甘みがあり、何も知らない子供だとうっかり手をだしてしまいそうな危険な雰囲気はあります。
ほんのり甘酸っぱいですが、変な臭みもあり、とても美味しいとは言えないのですが、逆に危険性を感じる味でもないので、そこは恐ろしいところです。
毒入り果実の謎
しかし、なんで実に毒があるんでしょう?
そもそも果実というのは実を食べてもらい、その実を糞として遠くまで運ぶことで、植物と動物の共存関係が築かれるわけですが、その実に毒を入れるというのは、実に意味不明な進化といえます。
配達員を呼びつけて殴り殺して、荷物が届かないと嘆くくらい意味不明です。
例えば、トウガラシは、本来ほ乳類には食べてもらいたくないために、カプサイシンという辛み物質を実の中に忍ばせる進化をしました。
鳥類は辛み受容体を持たないため、鳥類にのみ食べられ分布を効率的に広げることができるという、選択性を獲得した植物です・・・まぁその成分のおかげで、インド人を始め、今や世界中で栽培されているわけですが(笑)。
ともあれ、おそらくドクウツギもかつては、毒をモノともしない相棒がいて、繁栄をした時代があったのでしょう。ドクウツギの起源は恐竜絶滅、白亜紀末期あたりとされているので、この毒が一切効かないパートナーがなにかいたのではないかと。
現在はそのパートナーも失い、ひたすら誰も食べない(実際に鳥も食べない)誰得の毒入り果実を実らせては腐らせる不毛な結実をしています。
そのおかげで種子の発芽条件も厳しく、種子からの繁殖まで微妙・・・という、まさに進化の袋小路といった有様です。しかし、なんやかんや不器用ながらも、人類よりは遥かに先輩の生きた化石です。
危険危険とはやし立てて、ただでさえ絶滅危惧種の植物を追いやってしまっては元も子もありません。
別に全草に毒はありますが、触った程度では何も害はない植物なので、見つけてもそっとしておいてあげてください。
その毒性や、正体については「アリエナイ毒性学事典」で詳しく解説していますので、最後に改めてご紹介しておきます。
著者紹介

作家、科学監修。「科学は楽しい!」を広めるため科学書分野で20年以上活動。著作「アリエナイ理科」シリーズ累計50万部突破。原作を務めるコミックス「科学はすべてを解決する!!」も50万部を超える。著作「アリエナクナイ科学ノ教科書」が第49回・星雲賞ノンフィクション部門を受賞。週刊少年ジャンプ連載「Dr.STONE」においては漫画/アニメ共に科学監修を担当。TV番組「世界一受けたい授業」「笑神様は突然に・・・」NHK「沼にハマってきいてみた」等に出演。ゲーム実況者集団「主役は我々だ!」と100万再生を超えるYouTube科学動画を多数共同製作。独自YouTubeチャンネル「科学はすべてを解決する!」チャンネル約30万登録やTwitterフォロワー16万人以上。教育系クリエイターとして注目されている。関連情報は https://twitter.com/reraku
「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
「アリエナクナイ科学ノ教科書2」好評発売中です!
新刊「マンガでわかる! 今日からドヤれる科学リテラシー講座 教えて!夜子先生」好評発売中です!
宣伝
ニコニコ動画にて有料チャンネル「科学はすべてを解決する!! ニコニコ秘密基地」を開設しました!

「アリエナイ理科式世界征服マニュアル」が改訂版となって新発売されます!
「アリエナイ医学事典2」好評発売中です!
「アリエナイ医学事典 改訂版」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典3」、好評発売中です!
くられ先生の単著「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
工作系に特化した「アリエナイ工作事典」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典」改訂版が発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典2」、好評発売中です。